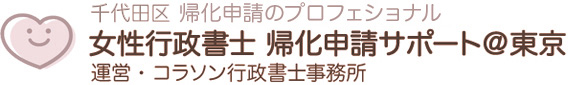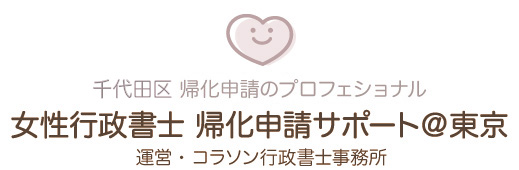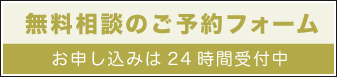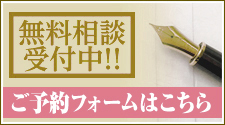トップページ > 3. 帰化要件(普通帰化)
3. 帰化要件(普通帰化)
3.帰化要件(普通帰化)
普通帰化が認められるためには、国籍法第5条に規定されている要件を満たす必要があります。ただし、規定の要件を満たす場合であっても、法務局の内規や裁量があるため、帰化申請できるかどうかは容易には判断できません。帰化申請については一人ひとりの状況に応じて事前に十分に検討する必要があります。
まずは一般的な帰化要件を見ていきましょう。以下の①~⑦を全て満たすことが要件となります。
①居住要件(国籍法第5条第1項第1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること
「引き続き」とは、日本を出国していた期間が、5年間の間に連続して90日以上なく、また年間で合計100日以上日本を離れることなく日本に住み続けていることを意味します。
上記の日数を超えて日本を離れていた場合は「引き続き」とは認められず、在留期間の中断とみなされます。
また、5年間のうち、就労系の在留資格(アルバイトではなく、正社員、契約社員、派遣社員などの雇用形態)で3年以上就労している必要があります。
②能力要件(国籍法第5条第1項第2号)
20歳以上であり、本国法でも行為能力を有していること
日本では、成人年齢は20歳以上ですが、国によって成人年齢は異なりますので、本国においても成人に達していることが必要とされます。
③素行要件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であること
年金、税金、贈与を受けた場合の贈与税などをきちんと納税していること、交通違反(駐車違反、スピード違反含む)、前科、犯罪歴がないことが要件となります。また、暴力団に加入していたり、密接に関わっている場合は素行が善良とは認められません。
また、素行要件の判定は、生まれた時から現在に至るまでの全ての期間が対象となりますので包み隠さず全てを報告する必要があります。
④生計要件(国籍法第5条第1項第4号)
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
ご自身又は生計を共にしている配偶者やその他の親族の収入によって、生計が成り立っていることが要件とされます。
ただし、永住申請と違い、年収要件はございませんので、年収250万円でも300万円でも、家賃、光熱費、食費等々差し引いて、安定的に収支が成り立つのであれば、生計要件を満たすことになります。目安としては、手取りで月収18万円程度で要件を満たすと考えられます。
⑤喪失条件(重国籍防止条件/国籍法第5条第1項5号)
現在国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと
日本は二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を取得した際には、元の国籍(本国籍)を失うことができる事が要件とされています。
⑥思想要件(国籍法第5条第1項第6号)
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり加入しているような方は帰化が許可されないことになります。
⑦日本語能力
国籍法からの要件ではありませんが、日本語の能力が求められます。
帰化後は日本人として生きていくことになりますので、選挙の際の投票用紙への記入、その他日常生活で日本人として一般的に暮らしていくことができる程度の日本語の能力が必要となります。
帰化申請後、審査官との面接がありますので、その際に日本語で受け答えができる日本語のレベル(小学校3~4年生程度の日本語能力。日本語能力試験(JLPT)ですと、N3~N4レベル。)は習得する必要があります。
以上7つが通常の帰化要件となります。
以下に普通帰化の要件をまとめてみましたのでご参照ください。
|
|
7つの要件 |
内 容 |
|
1 |
居住要件 |
5年以上日本に住んでいること |
|
2 |
能力要件 |
現在20歳以上であり、本国法でも成人に達していること |
|
3 |
素行要件 |
素行が善良であること 具体的には以下の素行について審査されます。 ‐運転履歴 ‐交通事故 ‐前科・犯罪履歴 ‐破産歴 ‐家族の素行 親族に暴力団等がいる場合は不許可になる場合があります。 ‐年金支払状況 ‐納税状況 直近1~2年の所得税、住民税を滞納されている場合には必ず完納して下さい。また、会社経営者の方は直近2~3年分の法人税、法人都民税、法人区民税、法人事業税等を必ず完納してください。 |
|
4 |
生計要件 |
自己、または生計を同じくする配偶者や親族の資産等で生活を営むことができること |
|
5 |
喪失要件 |
現在国籍を持っておらず、または、日本国籍の取得(帰化)によって現在持っている国籍を失うことができること (日本は二重国籍を認めておりませんので帰化した際には現在の国籍を離脱して頂くことになります。) |
|
6 |
思想要件 |
政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したり、そのような政党や団体を結成したり、これに加入したことがないこと (憲法遵守要件とたとえられたりします。) |
|
7 |
日本語能力要件 |
日本で日常生活をするために必要な日本語のレベル (小学校3~4年生程度の日本語能力。日本語能力試験(JLPT)だと、N3~N4レベル。) |
※急ぎのお問い合わせに関しては
お電話(03-6823-1855)でも対応させて頂きます